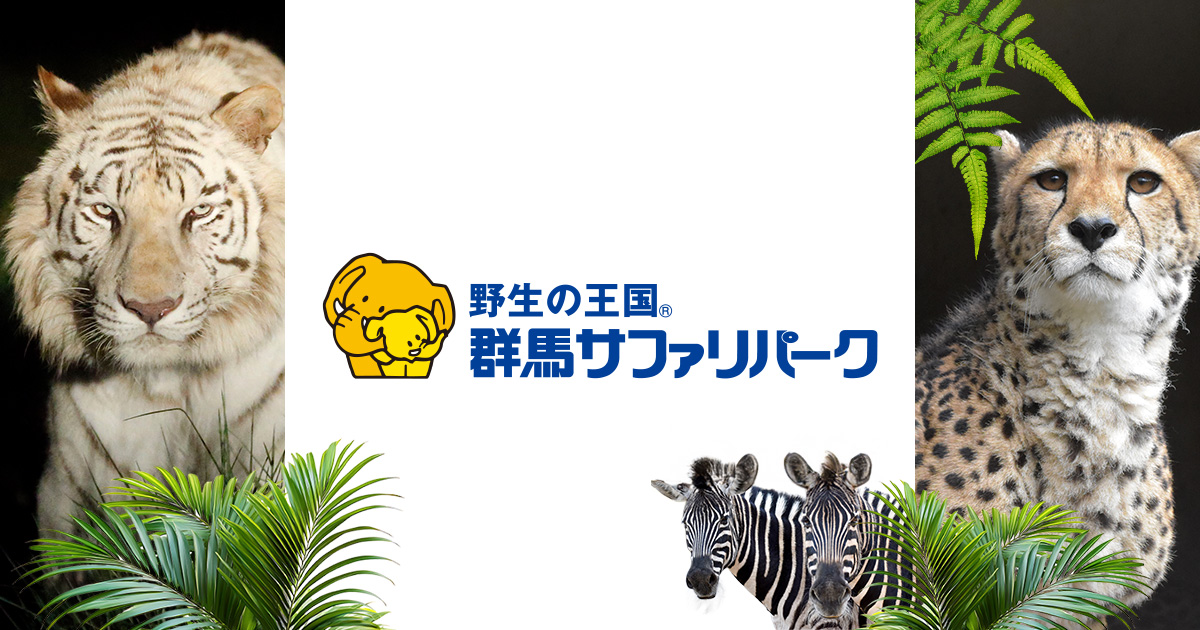ワピチの基本情報
英名:Wapiti
学名:Cervus canadensis
分類:鯨偶蹄目 シカ科 シカ属
生息地:ブータン、カナダ、中国、カザフスタン、キルギス、モンゴル、ロシア、アメリカ合衆国
保全状況:LC〈軽度懸念〉

オスの大きな角
北米とアジアに生息するワピチ。
彼らはとりわけ北米ではエルクと呼ばれます。
しかし、このエルクという言葉はヨーロッパではヘラジカを指します。
ちなみにヘラジカは北米ではムースと呼ばれており、ヘラジカとワピチはその呼び方が混同されがちです。

そんなワピチは、そのヘラジカに次いで大きなシカです。
オスは最大500㎏近くにもなります。一方メスは最大でも300㎏程度。
体サイズにおける性差は、ワピチでは著しいです。
このような性別によって形態が異なることを性的二型と言いますが、ワピチは体サイズだけでなく、あるもう一つの部分においても性的二型が見られます。
それが角です。
いくつも枝分かれした角はオスにしかありません。
シカの角はアントラーと呼ばれますが、ワピチのアントラーは最大で1.5mを超えます。
アントラーは毎年生え変わりますが、ワピチの場合、3月ごろ抜け落ち、その後新しい角が生え始めます。
成長段階の角の周りは表皮で覆われ、血が流れています。
この状態の角は袋角と呼ばれ、袋角の表皮は繁殖が始まる晩夏までに剥がれ落ち、角は骨質のみになります。
このようにオスとメスで大きく見た目が異なるワピチですが、これは繁殖システム(配偶システム)に大きく関係しています。
通常、ワピチのメスは複数のメスとその子供で群れを成します。
一方のオスは若ければ若いオス同士と群れを作り、成熟オスは単独で行動することが多いです。
しかしこれが繁殖期になるとオスメス入り乱れた状態になります。
オスは特定のなわばりを持ちませんが、複数のメスを囲い他のオスから守ります。
この1頭のオスと複数のメスの群れはハーレム(ハレム)と呼ばれます。
オスはハーレムを守るために数㎞先まで聞こえる吠え声を上げたり、時には角を使って他のオスと闘争したりします。
こうしてハーレムを守ることができたオスはハーレム内のメスを独占することができるのです。
このように少数のオスが複数のメスを独占する、つまりメスをめぐるオスの闘争が激しい哺乳類では、性的二型が顕著となることが多いです。
同じような配偶システムを持つ鰭脚類でも、ワピチと同じように性的二型が顕著です。


ところで、メスをめぐる闘争のために発達したオスの角ですが、別の存在も魅了しています。
それが人間です。
中国やモンゴルでは袋角が伝統的な薬の原料として重宝され、1㎏100USD前後で取引されているようです。
角以外にもオスの性器やメスの尾、胎児も同じく薬の原料とされており、科学的根拠がないにもかかわらず多くのワピチが密猟され、かつての個体数の9割以上も減少しています。
対照的に北米では、増えすぎたワピチは植生を破壊し、生態系を不可逆的に乱すため、個体数管理を目的として管理された狩猟が行われており、毎年20万頭程度が捕獲されています。
個体数管理には狩猟以外の方法も用いられています。
イエローストーン国立公園ではオオカミの再導入が行われており、一部生態系の復活が観察されています。
オオカミの存在がどの程度ワピチの個体数調節、そして生態系の再生に影響しているかは議論がありますが、日本におけるオオカミ再導入の議論の際にも参照される貴重な例となっています。
ワピチの角一つとっても、そこには彼らの生態や人間の文化など、骨だけでなく様々なものが詰まっています。


ワピチの生態
分類
長らくアカシカ(C. elaphus)の亜種とされてきましたが、21世紀以降、両者は独立種として扱うことが一般的です。
ルーズベルトエルク(C. c. roosevelti)など8種程度が知られています。
生息地
北米とアジアの草原や森林、山地に生息しています。
北米ではかつて広く生息していましたが、西欧人の入植以降、狩猟により数を減らし、今では西部を中心に分布しています。
メキシコでは絶滅しています。
森林限界より上で見られることもあり、中国では標高5,000m付近でも見られます。
イタリアとニュージーランドに導入されています。

形態
体長は1.6~2.7m、肩高は1~1.5m、体重はオスが平均約330㎏、メスが平均約240㎏です。
春先に保護毛と下毛からなる冬毛を脱ぎ換毛します。
食性
夏には草本類、冬には木本類の枝や樹皮などを食べます。
実生や若木もよく食べるので、個体数の増加は森林維持に大きな影響を与えます。
飲み水は必須です。
成熟個体が襲われることは少ないですが、捕食者にはオオカミの他、クマやピューマがいます。
幼若個体はコヨーテやヤマネコに襲われることもあります。





行動・社会
薄明薄暮時に最も活発になります。
季節移動をすることもあり、夏には標高が高いところに、冬には谷などの低い位置に移動し、その距離100㎞以上になることもあります。
厚い積雪は嫌い、暑いと沼や池に浸かり涼みます。
捕食者から身を隠すため植生が生い茂る森林が必要ですが、餌場としては開けた環境を好みます。
嗅覚、視覚、聴覚が優れ、シカの中ではよく鳴く動物として知られています。
繁殖期を除くと、メスはメスとその子からなる群れを作りますが、群れサイズは環境により異なり、10頭程度から200頭以上と様々です。
繁殖
繁殖期は9月から10月初めにかけて見られます。
メスは240~262日の妊娠期間の後、15㎏程度の斑点模様がある赤ちゃんを一頭産みます。
群れから離れた茂みで出産し、しばらく過ごしますが、生後2週間ほどで群れに合流します。
生後2ヵ月までに離乳し、次の繁殖期までには独立していきます。
性成熟は1.5~2.5歳で、寿命は環境がいいと20年程度になります。

人間とワピチ
絶滅リスク・保全
ワピチは全体として増加傾向にあります。
地域によっては個体数の増加により生態系に被害を与えているところもありますが、反対に生息地の分断(北米)や密猟(アジア)などによって個体数が減少している地域もあります。
ワピチはIUCNのレッドリストでは軽度懸念の評価です。

動物園
日本では埼玉県の東武動物公園と群馬県の群馬サファリパークでワピチを見ることができます。